
「京菓子ハレモケモ。」事業の趣旨
上京区民会議と上京区役所では、地域に根付く和菓子の魅力を再発見してもらうため、連続企画「京菓子ハレモケモ。」をスタートしました。
名前には「京菓子をハレの日(特別な日)だけでなく、ケの日(日常)にも楽しんでほしい」という思いが込められています。
第1弾をかわきりに、今後も、和菓子を切り口にした企画が予定されています。
- 第2弾 令和7年12月20日(土) 上京文化絵巻第12巻「和菓子の記憶と物語」
- 第3弾 令和8年1月 上京和菓子店舗パネル展示(上京区総合庁舎)
- 第4弾 令和8年2月21日(土) 上京・京菓子マルシェ(元待賢小学校)
第1弾イベント概要
令和7年9月27日(土)、中秋の名月を前に「月見団子の謎解き親子さんぽ」を開催。
親子で区内を約3キロ散策しながら、和菓子にまつわる謎解きやクイズに挑戦しました。
学んで散策!「月見団子の謎解き親子さんぽ」
京都御苑 中立売御門~道喜門(どうきもん)「上菓子屋・おまん屋・お餅屋 ― の違いは何?」

朝9時から、20分おきに5つのチームが出発しました。
各回親子10名前後の参加者で、ガイドさんの案内の元、約3キロのコースを散策します。

中立売御門を出発し、道喜門、護王神社、鳴海餅本店を経由し、ゴールの京菓子司 塩芳軒(しおよしけん)を目指します。

お月見と言えば9月のイメージがありますが、太陰暦と太陽暦の暦のズレで、今年の中秋の名月は10月6日になることに驚く参加者。
その他、菓子伝来の由来や、上菓子屋さん、おまん屋さん、お餅屋さんの違い、「道喜門」のお話などガイドさんの説明を熱心に聞き、ヒントも参考にしながらクイズに答えます。

護王神社-「亥の子餅(いのこもち)」
京都御所の蛤御門を出て、烏丸通を西へ渡り、護王神社へ向かいます。護王神社は、和気清麻呂(わけのきよまろ)公を主祭神(しゅさいじん:神社の中で、最も中心となって祀られている神様)とする神社で、境内には和気清麻呂公がイノシシに助けられ足の怪我が回復したという故事から狛犬ではなく「狛(こま)イノシシ」が鎮座します。この故事から、足腰の健康を願う多くの方が参拝される神社として知られています。
この故事にちなみ、旧暦10月の亥の日に食べる「亥の子餅」も足腰の強さや無病息災を願う菓子として伝わり、護王神社とも深い縁があります。


鳴海餅-お月見団子はなぜ楕円形?
少し日差しはありましたが、秋晴れの美しい街並みを、鳴海餅がある堀川下立売へと進みます。


鳴海餅に入る前に、京都の伝統的な月見団子の形についてのクイズが出されました。
答えは・・・鳴海餅で確認しましょう!とのこと。正解のお菓子がどれなのか、みなさんわくわくしてきた様子です。

鳴海餅へ入ると、店内は名物の栗赤飯の時期でもあり、大忙し。
そんな中、お月見団子の形の秘密を鳴海力哉(なるみりきや)さんから教えてもらいました。

京都のお月見団子は、楕円形のお餅に、あんこがかかっている独特な形をしています。これは、何の形にみえるでしょうか?

中秋の名月は別名「十五夜」とも呼ばれます。さらに十五夜は秋の収穫に感謝することから、芋名月とも呼ばれており、里芋の形を模してお月見団子をつくったそうです。
また、月が綺麗に見える日は「十五夜」だけではなく、「十三夜」もあり、十三夜は栗名月、豆名月と呼ばれていることも知りました。
ちなみに令和7年の十三夜は11月2日です。
十五夜、十三夜両方のお月様を見ると縁起が良いと言われています。

歩いてきたので、お餅とあんこがとても美味しく、参加した子どもたちもペロリと食べていました。

堀川商店街~和菓子店 金谷正廣(かなやまさひろ)-秀吉公が称賛した真盛豆
鳴海餅を後にした一行は、堀川商店街を通り、塩芳軒へ向かいます。
途中、豊臣秀吉公が天正十五年の北野大茶会で「茶味に適す」と称賛された真盛豆(しんせいまめ)を作り続ける和菓子店「金谷正廣」のお店を通り、歴史がそばにあることを肌で感じました。

黒門通~京菓子司「塩芳軒」
かつて豊臣秀吉が築いた聚楽第の鉄門の別称「黒門」からその名が付いたという黒門通を進み、ゴールの京菓子司「塩芳軒」へ。

風情ある佇まいと黒い暖簾があたたかく迎えてくれました。


「月見うさぎ」という銘のお菓子と枝豆の形をした「すはま」、そしてお茶をご用意いただきました。
白い生地にこしあんが包まれた上用饅頭の月見うさぎの形はまん丸。丸いお月様にうさぎがお餅をついている姿を想像します。ちなみに、冬になると同じうさぎでも、形は楕円形でつくられ「雪うさぎ」という銘になるそうです。美しいですね。
すはまは、きな粉を主原料とした和菓子で、古くから茶席で供されているお菓子ですが、十三夜が豆名月とも言われていることから、枝豆の形をしています。
また、「歩いてこられたのでお疲れでしょう。」と冷たいお茶の配慮も嬉しかったです。
何より、高家さんのお話のとおり、「しつらえを楽しむ」ことが大事にされており、床の間のお軸、お花、すべてが秋やお月見を感じさせました。
季節や風景が思い浮かぶことが京菓子のだいご味だと言います。


最後に

最後に、暗号を解読し隠された言葉を見つける謎解きのカードが配られ、解散となりました。
上京区内には、和菓子屋さんがたくさんあります。
ハレの日もケの日も、おいしく楽しんでもらえたら嬉しいです。
参加者の声
参加者からは、
- 和菓子以外のまちの歴史も知れて楽しかった、美味しくておみやげも買ってしまいました。
- 謎解きが好きで参加しました。お団子の形に意味があると知ってびっくりしました。
- 普段から和菓子が好きなので、知らないお店も知れてよかったです。またお店に行ってみようと思います。
という声がありました。
歩いて学んで食べて、さまざまな目線で和菓子をとらえることができて、上京区への関心も深まったのではないかと思います。
レポーター
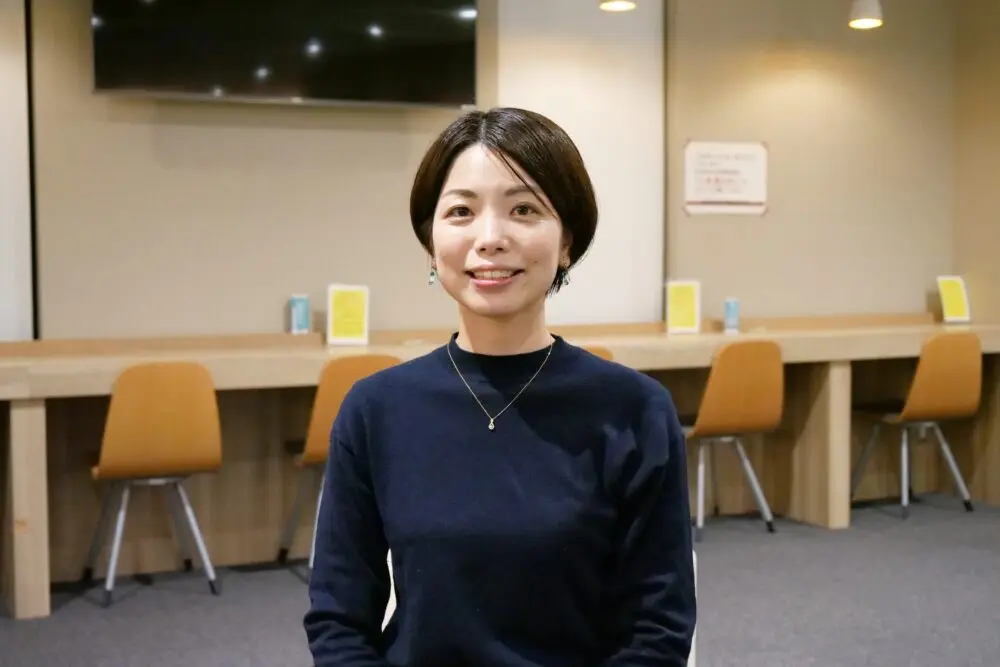
お店の方にお話を聞かせてもらうことができ、贅沢な時間でした。
謎解きのこたえは、後日参加された方に届くそうです。
ちなみに、私の謎解きは自信があります!




